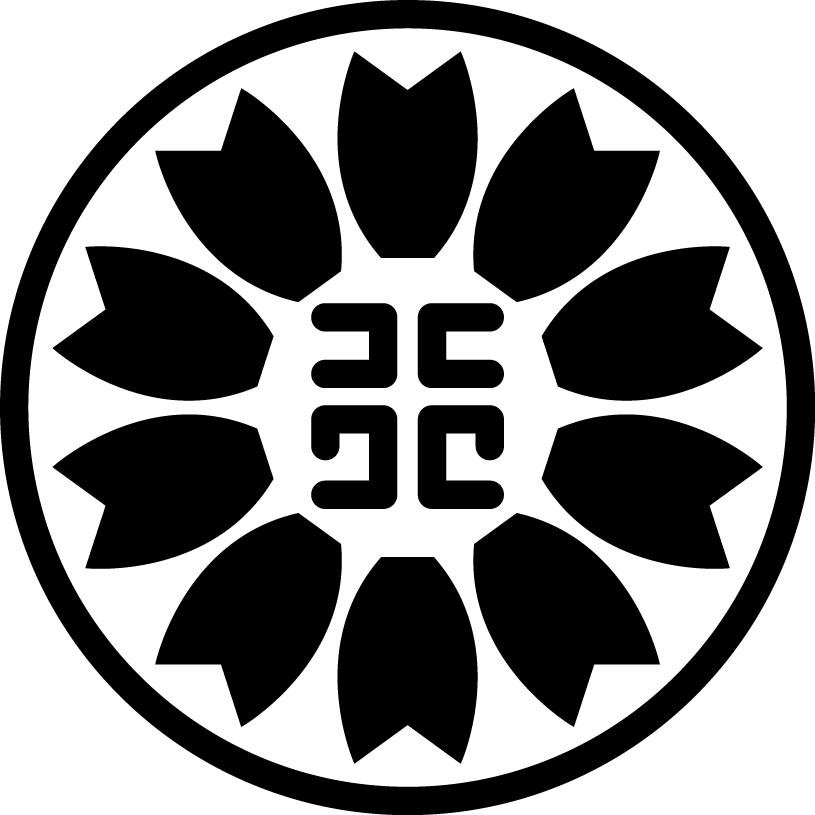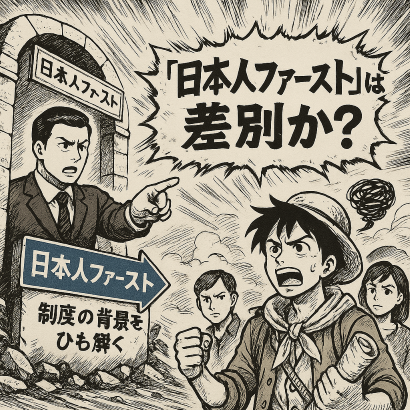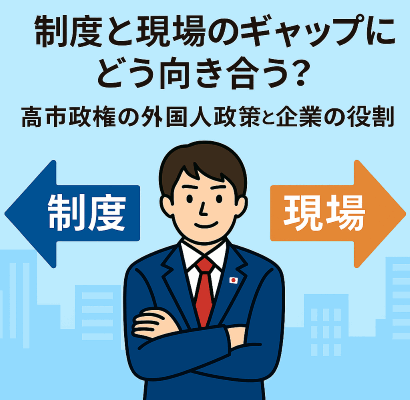✍️ 特集第1回:「日本人ファースト」は差別か?—制度の背景をひも解く
■ はじめに:その言葉にざわつく理由
「日本人ファースト」——
外国人雇用や地域共生が広がる中で、この言葉は賛否両論を呼びがちです。
「外国人ばかり優遇されていないか?」という疑問や、
「そもそも“日本人が優先される”のは当然だ」という声。
参政党など一部政治勢力はこの考えを鮮明に打ち出しています。
「国民が優先されるのは当然」「日本の文化や秩序を守るべき」といった論点。
それが差別か、当然の権利か——
その“制度的背景”をまずは見つめてみましょう。
■ 制度に刻まれた「優先原則」
「日本人ファースト」という言葉自体は、法律用語ではありません。
しかし制度の中には、“国籍や定住の有無”を基準に運用が分かれる項目が多く存在します。
例:
- 雇用助成金・職業訓練:日本人対象が中心/外国人対象の制度は別枠
- 災害時の情報提供・避難所運営:日本語話者が前提
- 社会保障の加入資格:国籍や在留期間により制限あり
これは差別ではなく、「国民を優先する制度設計」と言えるものです。
背景には、財源への負担原則、居住期間の長さ、国民義務との整合性があります。
■ 「差別」と「制度設計」の境界線
問題はここからです。
制度上の区分が、現場では「外国人は後回し」に映ったり、
逆に「外国人ばかり特別扱いされている」と捉えられることもあります。
外国人本人が感じる“線引き”と、
地域住民や企業担当者が感じる“納得できる理由”。
そこにズレがあると、「差別的だ」「逆差別だ」と言葉が強くなります。
参政党のような政治勢力はこの不満を代弁する形で、
「日本人優先は当然」という主張を、教育・福祉・治安などの政策に落とし込んでいます。
ただし、制度が“差別的結果”を生むなら、それは見直しの余地があります。
■ 現場の実感:「翻訳者」になる支援者たち
制度がどう設計されていても、現場では言葉を“翻訳”する人が必要です。
外国人社員や住民に対して、「なぜこうなっているのか?」を丁寧に伝えられる人。
一方で、企業や地域側に「なぜ不満が生じるのか?」を逆に伝える人。
制度と現場の両方を知る支援者は、まさに“制度と感情の翻訳者”として重要な役割を担っています。
摩擦を減らすには、ルールの説明だけでなく、関係性の構築が必要です。
■ おわりに:優先か共生か、その問いの先へ
「日本人ファースト」という言葉が制度にどう現れているか、
それが差別か、当然か、という問いには簡単な答えはありません。
でも、“説明できる制度”と“納得できる関係性”があれば、
言葉の衝突は減り、「共生」への一歩が踏み出せます。
次回は、地域で起こる摩擦と、外国人を“生活者”としてどう受け入れるかを探ります。