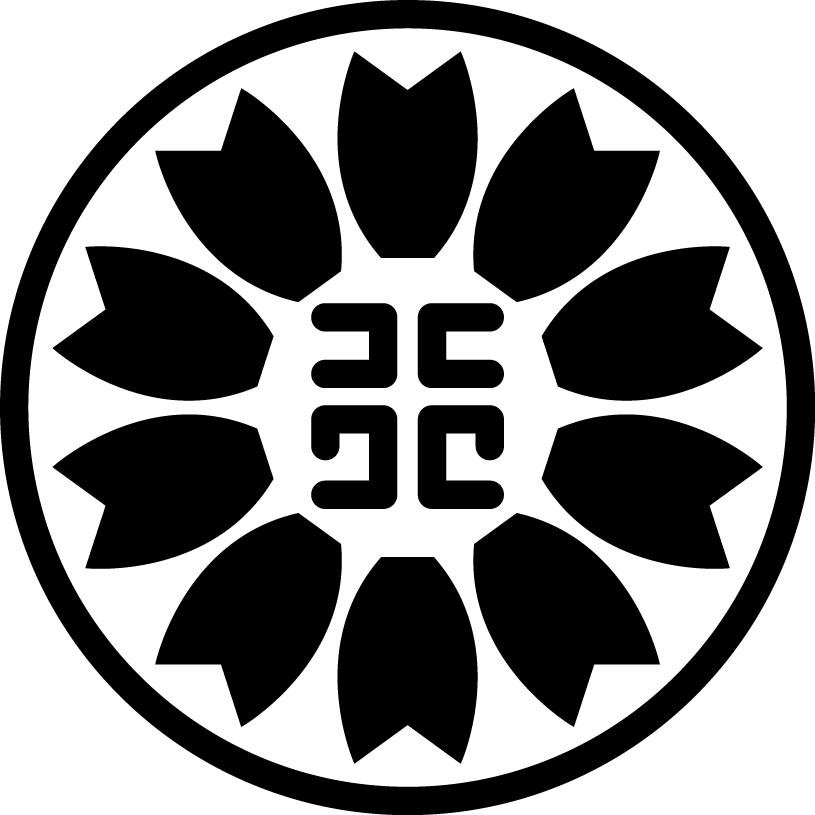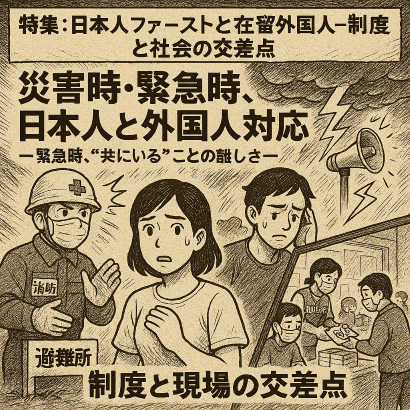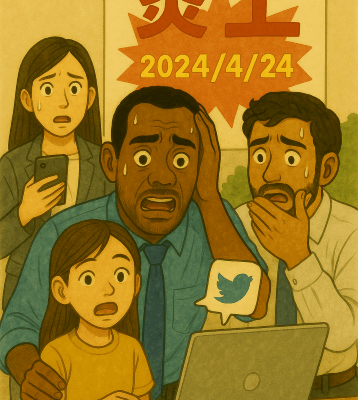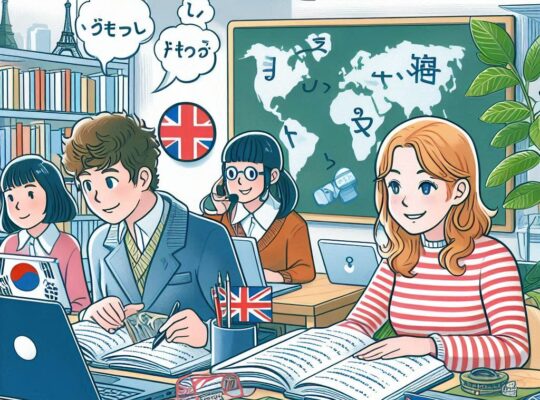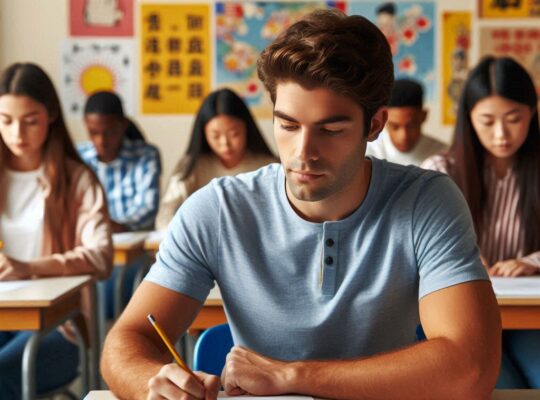🌀第3回:「災害時・緊急時、日本人と外国人対応の交差点」
―緊急時、“共にいる”ことの難しさ―
2020年の豪雨災害、2021年の地震、そして2023年の能登半島地震。繰り返される自然災害の中で、避難所や情報伝達において「誰が守られるのか」という問いが、何度も浮かび上がった。
避難所で戸惑うベトナム人技能実習生。マスク不足の中、配布対象から漏れる留学生。伝達されない警戒警報。制度設計における“想定外”は、しばしば外国人を取り残す。
🔍制度の穴と現場の工夫
- 災害時の情報発信、多言語対応は道半ば。
- 「自助・共助・公助」の枠に外国人が組み込まれていない。
- 一方、自治体やNPOによる翻訳支援、避難誘導、炊き出しなど、現場では独自の工夫も。
🧩生活者視点が必要な理由
「助ける側・助けられる側」という構図では限界がある。
同じ街に住み、同じリスクに晒される存在としての外国人視点が、ようやく制度に問われ始めた。
企業の防災訓練に外国籍社員の参加が求められるようになり、一部自治体では通訳ボランティアの登録制度が始まっている。
💬現場の声から
「避難所では、英語ができる人が呼ばれた。でも韓国語が分かる人は誰もいなかった。」
「制度はあるが、現場は混乱する。そのとき頼れるのは、隣にいた日本人だった。」
“制度と現場の交差点”にあるのは、言葉・文化・立場を超えた人と人との助け合い。しかしそれが偶発的であってはならない。制度の裏付けと平時からの関係性こそが、災害時の命を分ける。