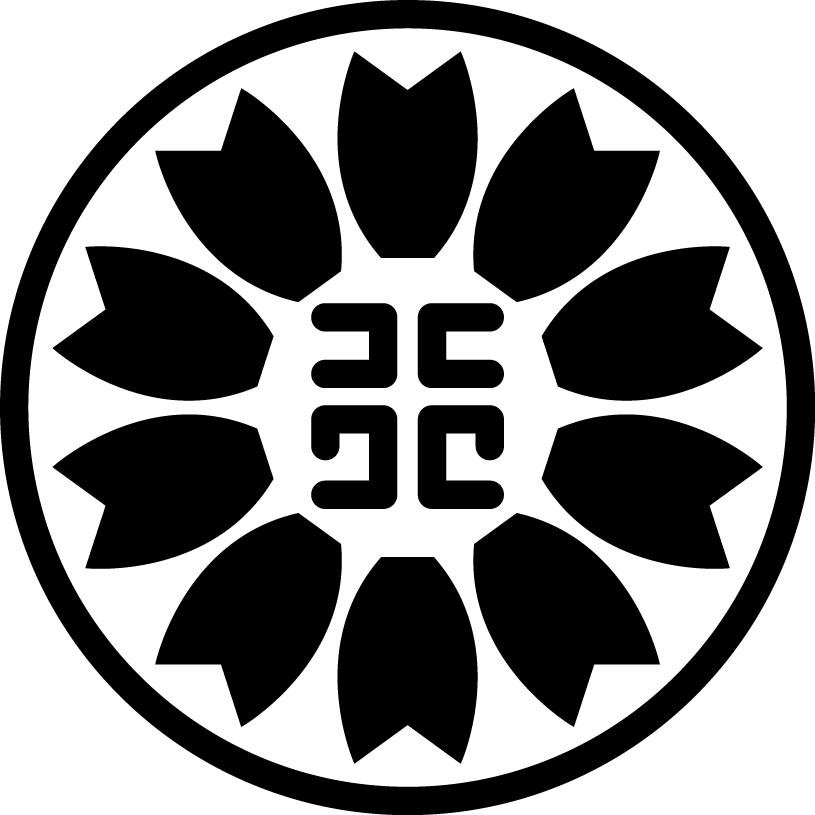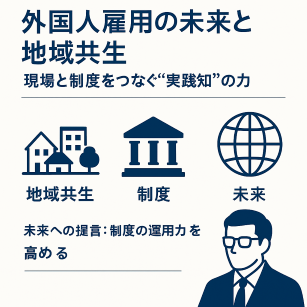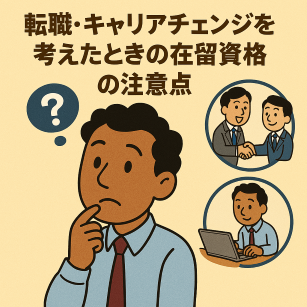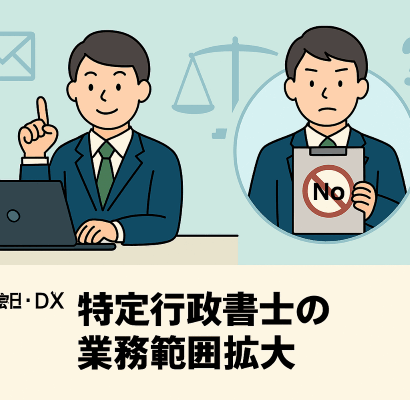8.「外国人雇用の未来と地域共生〜現場と制度をつなぐ“実践知”の力」
はじめに:制度と現場の“間”にこそ可能性がある
外国人材の雇用は、制度の理解だけでは不十分。
現場の声、本人の希望、企業の課題、地域の空気感——
それらをつなぐ“実践知”こそが、持続可能な雇用と共生の鍵になります。
これまでの振り返り:制度×現場×テクノロジーの融合
| 回 | テーマ | キーワード |
|---|---|---|
| 第1回 | なぜ今、外国人雇用にAI・DXが必要なのか? | 翻訳アプリ・やさしい日本語変換ツール・デジタル化 |
| 第2回 | 採用・面接・マッチングにAIを活かす方法 | リアルタイム翻訳アプリ・AIによる性格診断・AIマッチング機能 |
| 第3回 | 外国人材の定着支援にDXを活かす | AI音声読み上げ・勤怠管理アプリ・相談チャット |
| 第4回 | 在留資格の更新・変更手続きとその注意点 | クラウド管理・ジョブカン・ChatGPTによる自動生成 |
| 第5回 | 外国人材との信頼関係づくりとコミュニケーションの工夫 | ChatGPTによる「やさしい言い換え」・アンケートのForms活用・社内SNS |
| 第6回 | 制度改正や最新情報を現場にどう届けるか | 社内SNS・eラーニング・社内ポータル |
| 第7回 | 外国人材のキャリア支援と企業の成長をつなぐ制度活用 | AIで“個別支援”・社内ポータル |
👉 そして第8回は「地域との共生」と「未来への提言」
地域共生の視点:企業だけでなく“まち”の課題でもある
- 🏘️ 外国人材が地域に住み、生活することで生まれる接点
- 🏥 医療・教育・交通など、制度外の“暮らしの壁”
- 🗣️ 地域住民とのコミュニケーション不足による誤解や孤立
👉 行政書士としての役割:企業と地域の“翻訳者”になる
未来への提言①:制度の“運用力”を高める
- 制度は「使えるか」より「どう使うか」が重要
- 企業・本人・地域の三者にとっての最適解を探る
- 行政書士が“制度設計者”として関わることで、現場に即した運用が可能に
未来への提言②:AI・DXを“共生ツール”として活用
- 🧭 翻訳・やさしい日本語で地域との橋渡し
- 📱 地域情報・生活支援を多言語で提供(LINE・Web)
- 🧠 AIによる相談・ナビゲーション機能で孤立防止
👉 テクノロジーは“人と人をつなぐ道具”として使う
未来への提言③:行政書士の“実践知”を社会に還元
- 制度と現場を知るからこそ、提言ができる
- 多文化共生・地域づくりの担い手としての可能性
- 情報発信・ブログ・イラスト・AI活用で“伝える力”を磨く
おわりに:シリーズを終えて
この8回のシリーズを通じて、私は「制度と現場の間にあるリアル」を伝えてきました。
外国人材の雇用は、制度だけでも現場だけでも語りきれません。
だからこそ、行政書士として、現場に寄り添い、制度を活かし、テクノロジーを使いこなす——
そんな“実践知”をこれからも発信していきます。