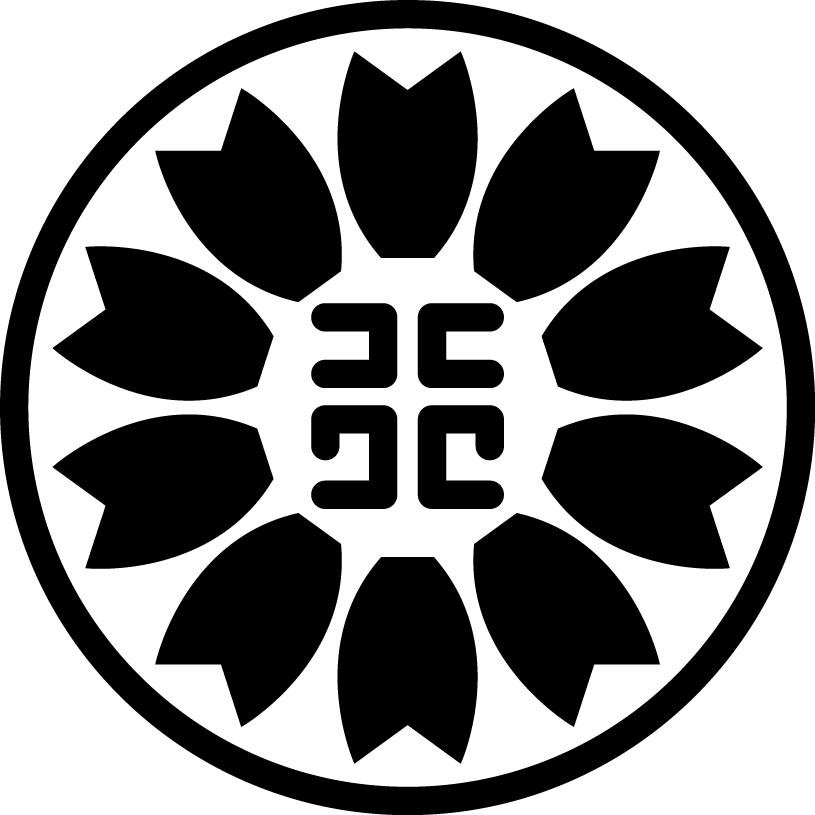第3回:在留資格はどう取るの?
企業が採用する前に知っておきたい手続きと注意点
外国人材の採用を検討する企業にとって、「在留資格」は避けて通れない重要なテーマです。制度の壁を乗り越えるには、正確な知識と現場に即した対応が欠かせません。今回は、在留資格取得の基本から、企業が押さえておくべきポイントまでを解説します。
📝 在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動するための「許可の種類」です。就労可能な資格は約20種類あり、活動内容によって分類されています。
| 在留資格の例 | 主な活動内容 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳、エンジニア、マーケティングなど |
| 特定技能 | 介護、外食、建設などの特定分野 |
| 技能 | 調理師、建築職人など熟練技能者 |
| 経営・管理 | 会社設立・運営 |
🛂 取得の流れ(企業が採用する場合)
- 採用内定・雇用契約の締結
- 雇用条件を明確にし、契約書を準備
- 在留資格認定証明書の申請(COE)
- 企業が入管に申請。審査には1〜3ヶ月程度
- 外国人本人がビザ申請(海外在住の場合)
- COEを使って現地の日本大使館・領事館で申請
- 入国・在留カードの取得
- 入国時に在留カードが発行され、就労開始可能に
つまり、在留資格(在留カード)は入国時にビザを元に発行されます。種類に応じた有効期限が記載されています。
⚠️ 注意すべきポイント
- 職務内容と在留資格の整合性
→ 例えば「通訳業務」で採用するなら、「技術・人文知識・国際業務」が適切。資格と業務が一致しないと不許可になることも。 - 申請書類の不備・不一致
→ 雇用契約書、会社概要、業務内容説明書など、細部まで丁寧に準備を。 - 在留資格の更新・変更にも注意
→ 業務内容が変わった場合は「資格変更」が必要。放置すると不法就労になるリスクも。
💡 企業ができる支援とは?
- 制度理解の共有
→ 採用担当者だけでなく、現場責任者にも制度の基本を伝えることで、安心感が生まれます。 - 専門家との連携
→ 行政書士などの専門家と連携することで、申請の精度とスピードが向上。 - 外国人本人への情報提供
→ やさしい日本語や母語での説明資料を用意すると、本人の不安軽減につながります。
🗣️ 現場からの声
「制度は複雑だけど、現場での安心感づくりが何より大事。企業と外国人が一緒に壁を乗り越える姿勢が、信頼につながる」
次回は「在留資格の更新はいつまでにどういう手続きをすればいいの?」をテーマに、制度の特徴や行政書士のサポートについて紹介します。
制度と現場のギャップを埋めるヒント、ぜひお楽しみに。