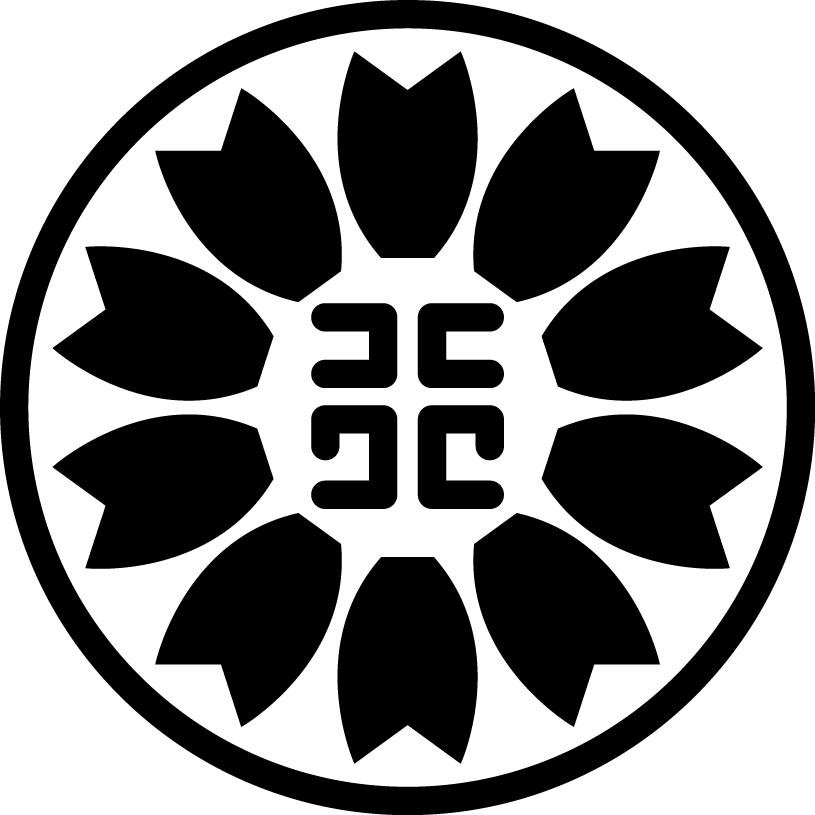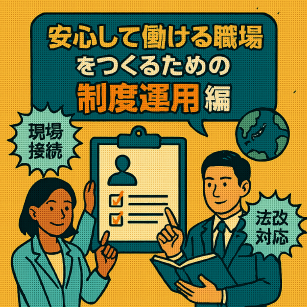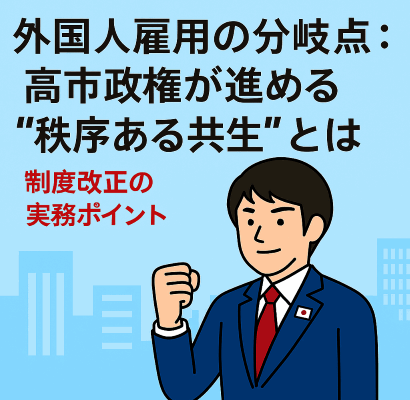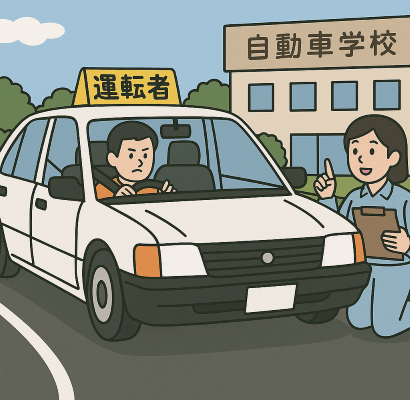── 制度運用編:制度を“使える仕組み”に変える視点
外国人材の雇用にあたって、企業がまず直面するのが「制度の複雑さ」です。技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務など、在留資格の種類ごとに要件や手続きが異なり、制度の理解だけでも一苦労。さらに、制度を理解しただけでは、現場で“使える仕組み”にはなりません。
本記事では、制度運用を「現場に根ざした経営支援」として捉え、企業が取り組むべき視点を整理します。
1. 制度は“運用”してこそ意味がある
制度は、紙の上で完結するものではありません。たとえば、特定技能制度では「支援計画」の策定が義務付けられていますが、実際にはその内容が現場で機能していないケースも多くあります。
制度運用とは、単に書類を整えることではなく、「制度を現場に落とし込むプロセス」を設計することです。つまり、制度と現場の“翻訳”が必要なのです。
2. 制度運用の3つの視点
制度を“使える仕組み”に変えるためには、以下の3つの視点が欠かせません:
🔹① 現場との接続設計
- 制度上の義務(例:生活支援、相談窓口)を、現場の業務フローに組み込む
- 担当者の役割を明確化し、属人化を防ぐ
- 現場の声を制度運用に反映する仕組みづくり
🔹② 多言語・多文化対応の整備
- 就業規則やマニュアルの多言語化
- 異文化理解を前提としたコミュニケーション設計
- 通訳・翻訳の外部連携や社内育成
🔹③ 継続的な制度アップデート対応
- 制度改正へのアンテナを張る(例:特定技能2号の拡大など)
- 外部専門家との連携による情報収集と対応策の検討
- 社内研修や勉強会の定期開催
3. 制度運用は“安心感”の土台になる
制度が現場で機能すれば、外国人材にとって「この会社はちゃんと支えてくれる」という安心感につながります。その安心感が、定着率の向上や職場の信頼関係の構築に直結します。
また、企業側にとっても、制度運用が整っていれば、監査対応や行政手続きの負担が軽減され、経営リスクの回避にもつながります。
4. 制度運用は“経営支援”である
制度運用は、単なる事務作業ではなく、企業の持続可能性を支える経営支援です。制度を理解し、現場に落とし込み、継続的に改善する。そのプロセスこそが、外国人材を“戦力化”するための第一歩です。
制度と現場のギャップを埋める支援設計は、企業の未来を支える“見えないインフラ”とも言えるでしょう。
締めの一言(知多半島の中小企業向け)
制度運用は、外国人材が安心して働ける職場づくりの土台です。知多半島の企業が地域と世界をつなぐ力を育むために、制度を“使える仕組み”へと進化させる視点が、これからますます重要になります。