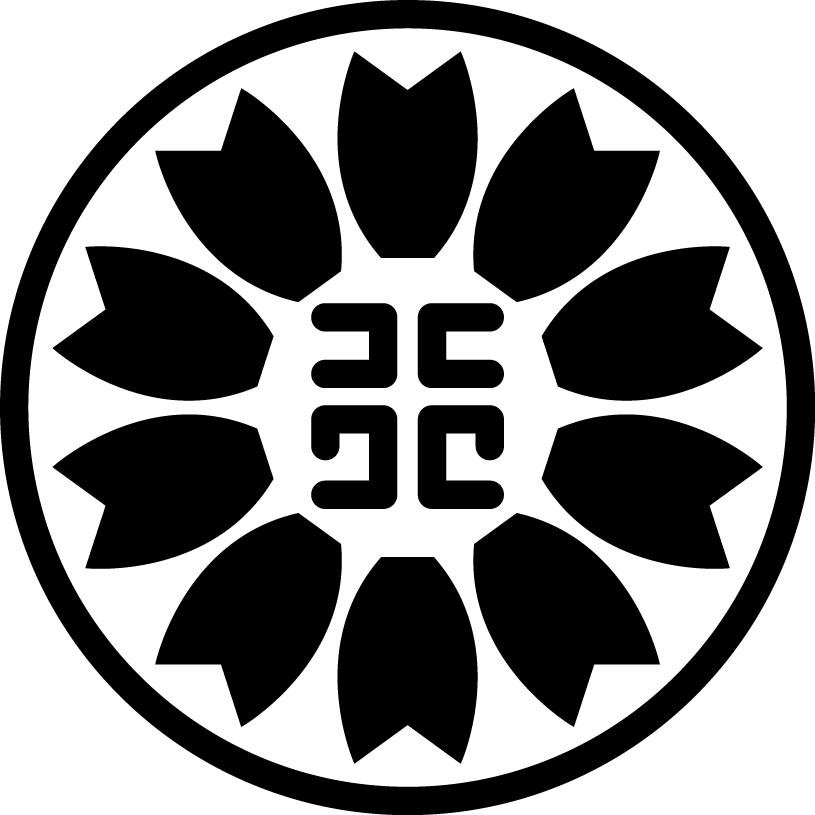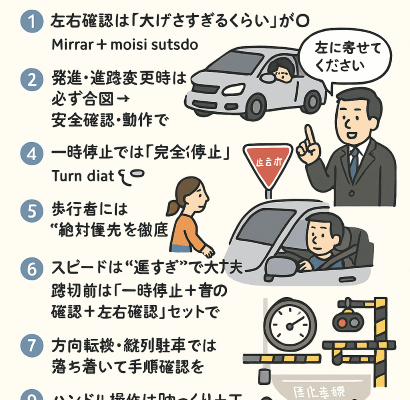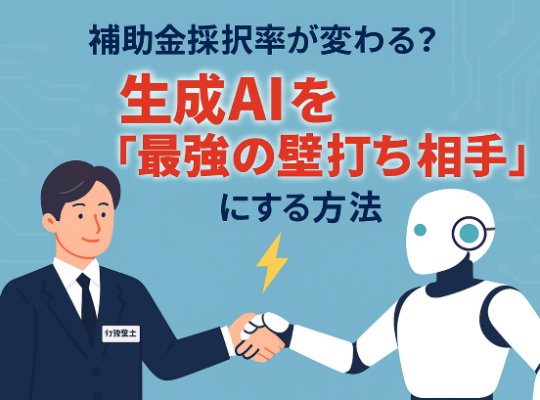制度は、企業にとっても従業員にとっても「安心の土台」となるべきものです。しかし、制度が複雑だったり、現場とのギャップが大きかったりすると、かえって「制度疲れ」を引き起こすことがあります。これは、制度の存在が“負担”や“混乱”の原因になってしまう状態です。
特に外国人雇用や中小企業の現場では、制度の運用に不安や戸惑いが生じやすく、会社側の支援者(人事担当者・現場責任者など)がその調整役を担うことになります。
今回は、会社側支援者が制度疲れを防ぎ、制度を“現場の力”として活かすための支援設計について考えてみます。
🧭 1. 制度の「目的」と「現場のリアル」をつなぐ
制度は理念や政策に基づいて設計されていますが、現場には日々の業務や人間関係、文化的背景など、独自の事情があります。会社側支援者の役割は、制度の目的を現場の言葉で翻訳し、納得感を持ってもらうことです。
- 制度の背景や意図を「やさしい言葉」で伝える
- 現場の声を拾い、制度運用にフィードバックする
- 「制度ありき」ではなく「現場ありき」の視点で支援を組み立てる
🛠️ 2. 制度を“使える”ものにするための伴走支援
制度があっても、使い方がわからなければ意味がありません。特に外国人雇用に関する制度は、言語や文化の壁もあり、現場での運用にハードルが生じがちです。
- 制度の活用事例を共有し、イメージを持ってもらう
- 書類作成や申請手続きの流れを整理し、現場に伝える
- 制度を「業務の一部」に自然に組み込む工夫をする
🤝 3. 制度と現場の“橋渡し役”としての会社側支援者
制度と現場の間には、しばしば「見えない壁」があります。会社側支援者はその壁を乗り越える“橋渡し役”として、両者の立場に寄り添うことが求められます。
- 制度の運用者(行政)と現場の実務者、双方の視点を理解する
- 現場の不安や疑問に対して、制度的な根拠をもって丁寧に対応する
- 支援者自身が制度を“使いこなす”ことで、安心感を届ける
🌱 4. 制度疲れを防ぐ「余白」と「選択肢」の設計
制度が“押しつけ”にならないためには、現場にとっての「余白」や「選択肢」が必要です。支援設計には、柔軟性と対話の余地を残すことが大切です。
- 一律の運用ではなく、現場ごとのカスタマイズを許容する
- 「やらなければならない」ではなく「こうすればできる」の提案型支援
- 制度の“使い方”を現場と一緒に考えるプロセスを設ける
✍️ おわりに──支援者を支える支援のかたち
会社側支援者が制度と現場の間に立ち、日々調整を重ねている姿は、まさに“橋渡し役”そのものです。しかし、その支援者自身もまた、制度の複雑さや現場の多様性に悩み、孤立しがちです。
次回は、そんな会社側支援者を支える「外部支援者」としての行政書士の役割について掘り下げてみたいと思います。制度運用と現場支援の両立を目指す企業にとって、行政書士はどんな伴走者になれるのか──その可能性を一緒に考えていきましょう。