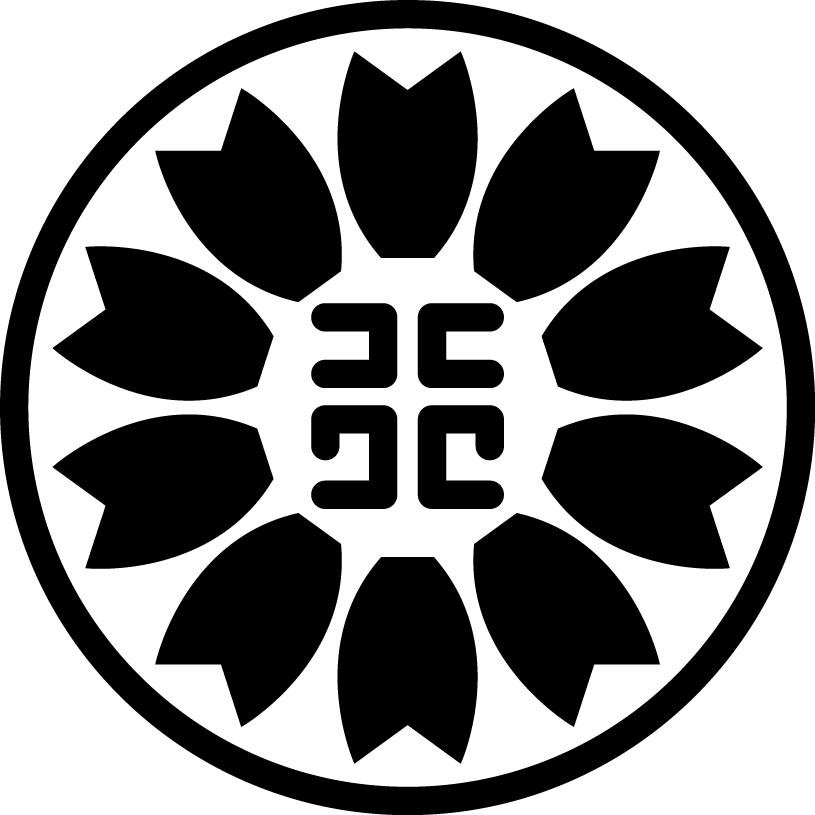〜「伝える」から「共に備える」へ〜
はじめに
地震・台風・豪雨など、災害が多い日本。
愛知県に住む外国人にとっては「情報が届かない」「避難所のルールがわからない」「文化的配慮がない」など、災害時に孤立しやすい現実があります。
本記事では、愛知県内で暮らす外国人住民が安心して災害に備えられるよう、行政・地域・企業ができることを整理します。
🧭 なぜ今「外国人向け防災情報」が重要なのか?
- 外国人住民は災害時の“情報弱者”になりやすい
愛知県では約29万人の外国人が暮らしており、言語や文化の違いから災害情報の理解に不安を抱えるケースが多く見られます。 - 多言語対応がある地域では「安心感」が高まる
あいち多文化共生ネットや名古屋国際センターなどが提供する多言語防災情報は、外国人住民の安心感につながっています【¹】【²】。
📢 愛知県で活用できる防災情報・ツール
| ツール名 | 内容 | 対応言語 |
|---|---|---|
| あいち多文化防災ポケットガイド | 災害時の行動や備えを簡潔に紹介 | やさしい日本語・英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語など |
| 名古屋市ハザードマップ・防災ガイド | 地震・洪水・津波などの災害リスクを地図で確認 | 英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語など |
| Safety Tips(アプリ) | 緊急地震速報・避難情報などを通知 | 14言語対応(英語・中国語・韓国語・ベトナム語など) |
| NICやさしい日本語防災マニュアル | 災害時の行動をやさしい日本語で解説 | 日本語中心(視覚的にわかりやすい) |
👉 詳細:あいち多文化共生ネット|防災情報【¹】
👉 詳細:名古屋国際センター|防災啓発資料【²】
🧩 現場支援者ができること
- やさしい日本語+母語の併記で情報発信
- 避難所運営マニュアルに「文化的配慮項目」を追加
- 外国人住民を「共助の担い手」として防災訓練に巻き込む
- 企業・自治体・地域団体の連携による多言語支援体制の構築
✍️ まとめ
防災は「伝える」だけでは足りません。
外国人住民が「理解できる」「行動できる」「地域とつながれる」仕組みづくりが、真の安心感につながります。
制度と現場のギャップに向き合う克哉さんのような支援者が、地域のレジリエンス(回復力)を高める鍵になると感じます。