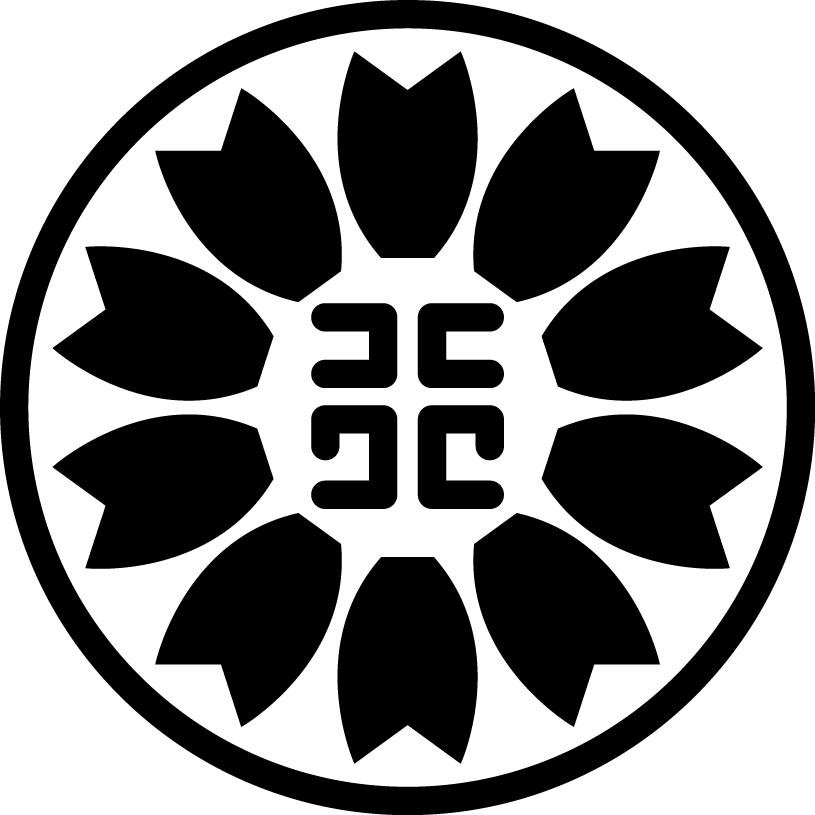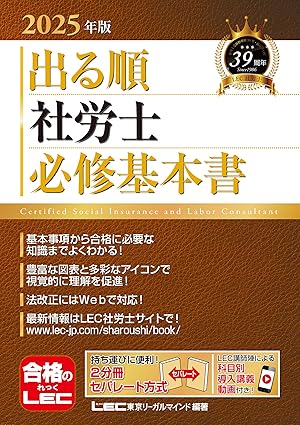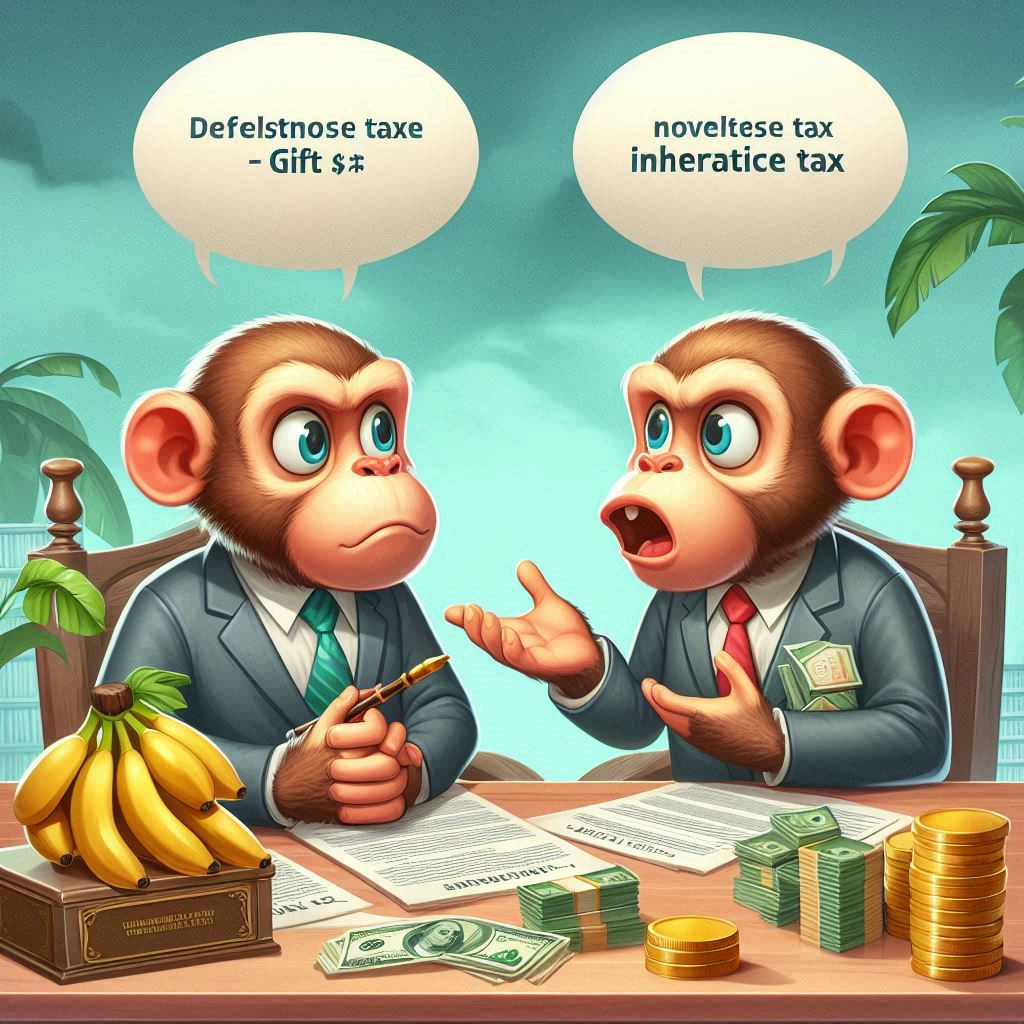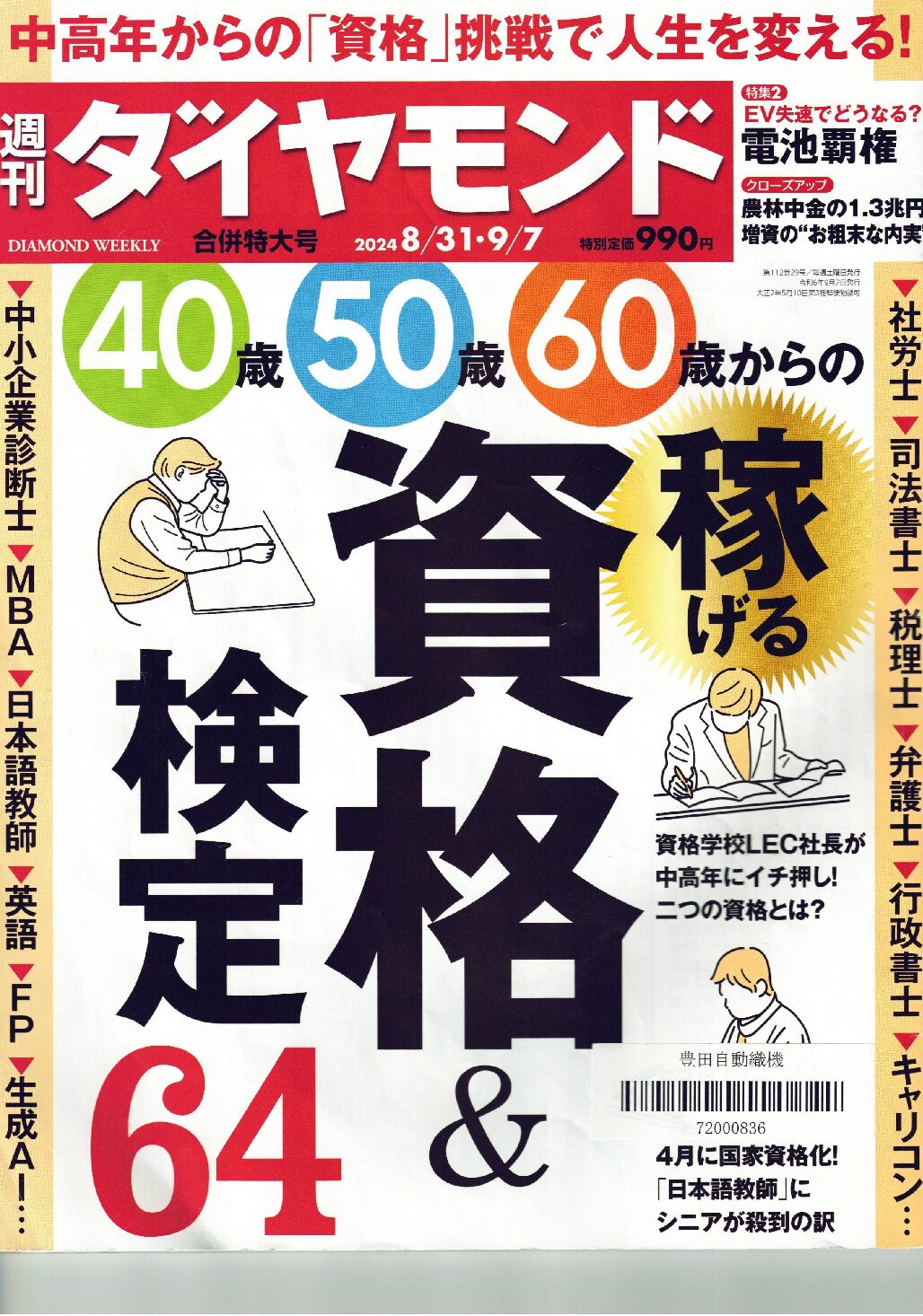今回からは「社会労務士」の勉強について書いていきます。
行政書士とのダブルラインセンス候補として相性がいいといわれる社会労務士ですが、
それは会社設立時には、開業のための定款作成や各種申請は行政書士ができますが、設立時には社会労務関係も必要となるため、そのどちらも資格を持っていればワンストップでお客様にもメリットがあるし、業務の単価も上げることができるからということです。
また社労士の場合は顧問契約が一般的なので、その場限りでなく関係を続けることができ、また将来の行政書士業務の受注にもつながることがあるそうです。
1回目の今回は、ばくっとした社労士試験の勉強について説明します。
まず、試験は毎年8月の後半の日曜日に行われます。なのでもし行政書士が落ちていたとしても、今年両方を受験することができそうです。(中小企業診断士は2次試験が11月にあるためもろ被りするのでその場合は社労士を受けようかと考えています)
なんてことを考えているとあっさり両方とも落ちるということになるかもしれませんが、行政書士だけでこれから1年というととても集中力心が持ちそうもないので一緒に何かは受けたいと思っています。
話を社労士試験に戻すと、社労士試験も行政書士と同じように全体の6割を取ればよい、というのですが、実は科目ごとの足切りがあるのです。それも科目数が多いので、結構引っかかる人も多いそうです。なので苦手な科目(分野)を作らないのが大事です。
その点自分は、得意もなければ苦手も少ないというアベレージ型なので、何とかなるかなと期待しています。願望ですが、苦手意識を持たないのは大切です。
あと、労務士試験のYouTubeをいろいろ見ていると、暗記が多いそうです。数字もちゃんと覚えなければならず、逆に数字問題が出たらラッキー問題と思えるよううじゃなければならないという話もありました。
数字なんて早く覚えてもすぐ忘れてしまうので、直前勝負かと思います。
もちろんそれまで勉強しないわけではなく、理解と数字以外の記憶はそれまでにしっかりやる所存です。
2回目以降は各分野ごとにポイントを見ていきたいと思います。
ちなみに使用しているテキストは、LECの「2025出る順社労士」です。
中身の構成がとても理にかなっていると感じるので私との相性は良さそうです。
今はテキストだけで問題を解いていないので、本当に受験するなら問題集も購入して進めなければなりません。行政書士が落ちたらです。